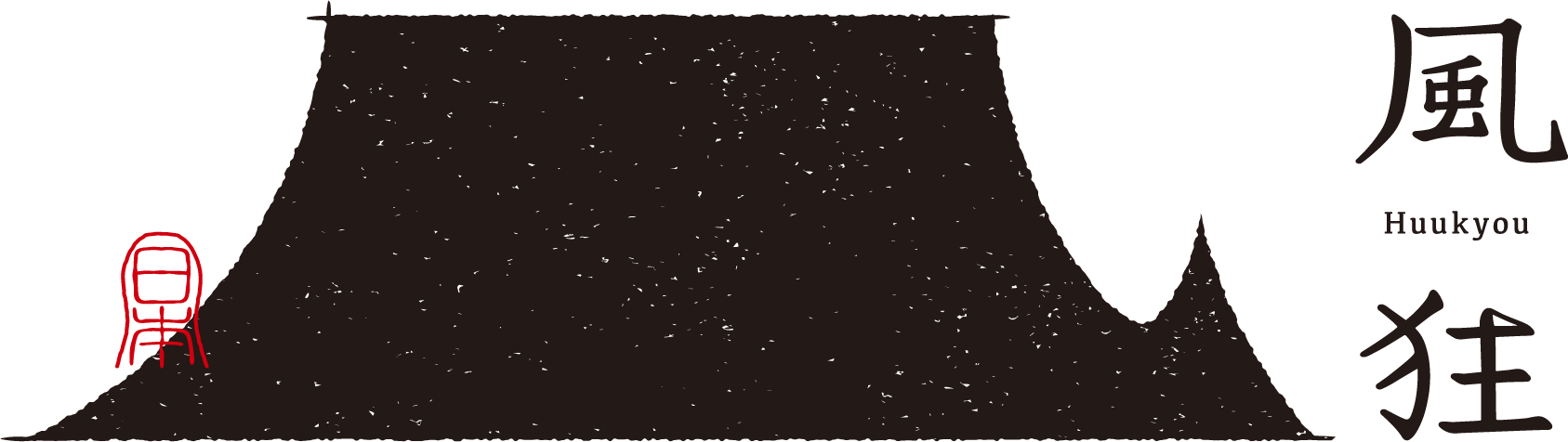キャンドルにはじまり、新たに販売を開始したお香と、偶然にも香りものの商品展開が続きました。フレグランス関連のアイテムを作ろうという話は特にありませんでした。ただよくよく考えると、香りというものは日本人が古くから兼ね備えてきた繊細な感性を表現しやすかったように思えます。
史実を確認しても、古くからの日本人と香りの結びつきがみてとれます。日本の香りの歴史は6世紀に始まり、河内国(今の大阪)で最初の香木が見つかります。その数年後、淡路島に香木が漂着。これには聖徳太子にまつわる話があり、彼はその香木を見て、一目で沈香(じんこう)だと見抜き、その沈香の香木で観音菩薩像の彫刻を命じたと言われます。仏教の供養で重要な仏具とされる三具足(さんぐそく)は、花立・燭台、そして香炉。仏教における香の位置づけの重要さを認識し、仏教による日本国の統治を目指した聖徳太子にとって、香木による観音菩薩像の製作は自然な流れであったのでしょう。
そうした仏教の祈りとしてのアイテムである香りが、平安時代以降、新たな側面を見せ始めます。たとえば、現代のルームフレグランスといえる”空薫物”(そらたきもの)や衣服に香りを焚き染める”薫衣香”(くのえこう)など、自己表現として香りを楽しむ傾向が生まれます。また、焚くものも香木から、練香(ねりこう)を焚くのが主流になっていきます。練香とは沈香をはじめとした粉末状の原料を蜜や梅肉などで丸い形状に練り固めたものです。その練香調合の代表的なものが六種の薫物(むくさのたきもの)と呼ばれ、そのうちの”侍従”という香りが、私たちが提供するアロマキャンドル・秋風のモチーフとなっています。
現在でもそうなのですが、当時練香調合における香材の選び方や調香方法は門外不出で、代々家内のみで伝承されるものでした。”侍従”もその例に漏れなかったのですが、源氏物語の中で薫物合わせ(たきものあわせ)の遊びをする場面があります。(薫物合わせとは、独自の香を持ちよってそれぞれの香りを鑑賞したり、その香りのイメージに合わせた和歌を詠んだりするものです。)主人公の光る君は、坎方(かんぽう)と拾遺(しゅうい)という薫物をつくります。そのうち拾遺は侍従の別称なのです。
鎌倉期の薫物の書では、以下のように侍従について説明があります。
「秋風蕭颯たる夕、心にくきおりふしものあはれにて、むかし覚ゆる匂によそへたり。」(秋風が吹く夕方、人恋しい季節にしみじみと心が惹かれ、昔のことが思い起こされるような香りにたとえられる)
侍従は、秋に吹く風の中に漂う甘美で切ない情感が香りに乗っていることが特徴的です。この侍従をはじめ、季節ごとの美しさとその中で移り変わる人々の情感が、香りで表現されてきました。

仏教伝来の同時期に日本に伝わった香りという文化は、当初祈りのためのものという位置づけでしたが、平安期を経る中で日本人の美意識と結びつくことで、日々の暮らしに浸透してきました。
香りは現在でも仏教における重要な三具足であることは変わりませんが、様々にかたちを変えて私たちの暮らしに彩りをもたらしてくれるものでもあります。